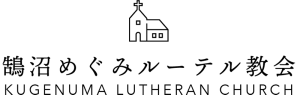自分を生きる

2025年11月16日(日) 説教
聖霊降臨後第23主日/成長感謝合同礼拝
ルカによる福音書21章5~19節
自分を生きる
今、自然界は紅葉でとても美しいです。私は、毎朝、一時間歩くようにしています。ここにいるときは海岸の方を歩いていますが、ルターハウスに行ったときは野川公園を歩きます。今、葉っぱを落として裸になる準備をしている木々がどんなに美しいのかわかりません。夏は緑の一色のように見えたのが、葉っぱを落とす時期になると自分の色が出て来て、種類によって色が異なる。それが調和を成してとても美しいのです。秋になって木が葉っぱを落とすのは自分を守るため、つまり、来年になって新しい枝を出すための淡々とした作業ですが、人だけがその知恵を生かして生きていないような気がします。そういう自分が情けなく思います。もう一度自然界に倣って、要らないものを手放す作業をしていきたいです。それが、自分の色を出せて、自分自身を生きることになるからです。私は、この木々の美しさに感動しながら、信頼についてもう一度学びました。自分に信頼を置くことはとても美しいことです。
さて、今日は「自分を生きる」というテーマで福音を分かち合いたいと思います。
イエスさまがエルサレム神殿の崩壊を預言なさると、人々はイエスさまに尋ねます。「先生、そのことはいつ起こるのですか。また、それが起こるときにはどんな徴があるのですか」と。それに対してイエスさまは、世の終わりが近づいたときに起こることや、気を付けるべきことをいろいろ話されました。そして最後に、「忍耐によって、あなたがたは命を得なさい」と勧めてくださいました。この言葉が新共同訳では、「忍耐によって、あなたがたは命を勝ち取りなさい」と訳されています。新共同訳に慣れていると、「命を得なさい」というのは何か空気が抜けた風船のような感じがします。「得る」というより「勝ち取る」と言った方が、何か一所懸命になれる感じがするからです。同じ言葉が使徒言行録22章でも使われています。そこにはこう書いてあります。「大隊長はパウロのところに来て言った。『あなたはローマ市民なのか。私に言いなさい。』パウロは、『そうです』と言った。大隊長が、『私は、多額の金を出してこの市民権を得たのだ』(使徒22:27‐28)。ここで大隊長が、『多額の金を出してこの市民権を得たのだ』というときの「得た」という言葉が、今日の福音書の「得る」ということばと同じ言葉です。ですから、どちらかというと、自分のために大切なものを獲得するために犠牲を払って確保するというときに使われています。当時はローマの市民権を持つことが力になるものだったようです。大隊長はローマの市民権を多額のお金を出して手に入れたのでした。
それに、「命を得る」というときの命とは、神さまとつながりの中で得るもの、永遠の命のことを指しています。永遠の命は誰にもすでに与えられていますが、それを見出すということです。自分の中に隠れている中から見出して守る義務が私にはあるということです。ここで私たちは、自分の中に、自分の命を守るための力がどれだけ蓄積されているのかが試されることになります。結論を申し上げれば、私たちはその力を十分確保しています。何十年も信仰生活をしてこられたのですから、その分だけ聖書を読み、祈りをし、礼拝の中で聞いた説教だけでも数えられないくらいです。内面に蓄積されている内なる力がないなど言えないはずです。ただ、使わないからそれがあるかどうかがわからないだけなのです。私たちは、自分にはそんなものなどない、自分は信仰が弱い者、そんな大事ができるはずがないと言ってすぐ人に頼り、神さまに頼ろうとします。しかし、実は、図書館に本が種類ごとに秩序正しく収められているように、私たちの中にも時にかなって使えるべき力がちゃんと備わっているのです。ですから、その力を相応しいときにどんどん発揮していく、発揮していくことが自分の命を守ることになります。
どんなときにその力を発揮するのか。それは、問題が起きたときです。たとえば、思わぬ事故に遭ってしまったとき、いつまでも自分の不注意を悔やんだり、相手の方を憎んだりしている場合が多いです。しかしそれは、問題解決にはなりません。
または、信じていた人に裏切られたとき、いつまでたっても憎んでいる場合があります。しかし、憎みの感情は自分の心と体を蝕むだけです。
ほかにもいろんなことが思わぬときに思わぬ形で私たちにふってきます。そのときに、私たちは事件の現場に戻ってくよくよするのではなく、知恵のある対応をしたいのです。そのためには、木々が要らなくなった葉っぱを思い切り落とすように、欲望や憎みの感情を自分から切り離すのです。「さようなら」と自分から切り離して、常に今から先へと心を持っていく。新しく歩き始めるのです。そうやってどんどん内面の力を発揮すれば、木々に負けないほど美しく輝くようになります。
すべてがうまくいくときは気づかないのですが、思わぬ出来事に遭う中で、人は自分の罪深さに気づきます。欲望の奴隷になって、感情的に物事を処理しようとするから、相手も自分も、そして周りの関係のない人まで傷つけてしまう。その自分はいったい何者なのか。ピンチな時だからこそ静かに留まってみるのです。しかし、自分を見つめようともせず、落胆したり嘆いたりする、それは、それだけ自分を疑っているということです。自分を抑える力がないことを現わしていることのほかに何ものでもありません。ですから、人は、神の存在を求めるのでしょう。自分が何者かを知るために、欲望や感情の世界から静けさの世界へ移るために、信頼その者でおられる神に出逢おうとしているのだと思うのです。
イエスさまは、「忍耐によって、あなたがたは命を得なさい」とおっしゃいました。命を得るためには忍耐が必要であるということです。「忍耐する」ということは、それほど易しいことではありません。それは、自分の欲望の振る舞いや感情的な言葉や行動を制御することですから、大変なことです。絶対に相手が悪いと思うことでも、相手のせいにしないで受け止める。上手くいかないことを生まれた環境や置かれた状況のせいにしない、子どもや親や家族のせいにしない、さらには自分自身を裁くようなこともしない。内なる力が試される場面はここですが、確かに、難しいことです。しかし、自分の命を勝ち取るためには、その忍耐することが人間側には必要であるとうことです。
イエスさまの時代、イエスさまのような新しい教えを説く人はいじめられ、迫害の対象になりました。特に大勢の人が群がって従うようになると、政治や宗教界の既存の権威主義者たちから敵対視されました。ですから、捕まって暴力を加えることによって、新しい教えを止めようとしました。イエスさまが十字架刑にさせられていったのは、そのような人々の妬みによるものでした。しかし、イエスさまはその人々の妬みに妬みをもって向き合ったのではなく、自分が死ぬことによって向き合い、そして終わりには命を勝ち取られました。
本日の福音書の中でイエスさまはこうおっしゃいます。「人々はあなたがたを捕らえて迫害し、会堂や牢に引き渡し、私の名のために王や総督の前に引っ張って行く。それは、あなたがたにとって証しをする機会となる。だから、前もって弁明の準備はするまいと、心に決めなさい。どんな反対者でも、対抗も反論もできないような言葉と知恵を、私があなたがたに授けるからである。」(12~15)と。
「どんな反対者でも、対抗も反論もできないような言葉と知恵を、私があなたがたに授けるから」とイエスさまは約束してくださっています。イエスさまは、自分の命は自分で得なさいと引き離しておられるようで、ご自分の名によって迫害を受ける者に、誰も反論できないような言葉と知恵を授けると約束しておられます。つまり、私たちが思わぬ出来事の中に置かれたときに、イエスさまに向かって心を開けば、そのための力をくださるというのです。
当時の弟子たちのように、私たちがイエスさまの名を信じるという理由で、牢に入れられたりするようなことはありません。今の日本の中で、めったにそう言うことは起きませんが、先ほど申しましたように、イエス・キリストの名のものに生きる者として、思わぬことに出遭わされたとき、さあ、どうするか。人や自分のせいにして弁明を並べるのか、それとも、自分の内面に語り掛けることによって、知恵のある結論を生み出していくのか。私たちが自分の内側を覗こうとしない限り、イエスさまの知恵のある言葉は聞こえてこないことでしょう。
「私を生きる」ということは、人や自分を裁きたい感情的なものを自分から切り落とすときに可能になります。私たちの中にはそうできる力があります。イエスさまが約束してくださっている、その力を発揮してこそ、私たちは自分の命を再び見出して自分を生きる人になります。そして、そのとき、不幸のように思えた一つ一つの出来事の中に神さまが共におられたことに気づかされることでしょう。
Youtubeもご視聴下さい。