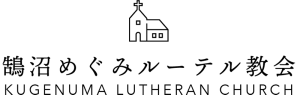留まるべきところ
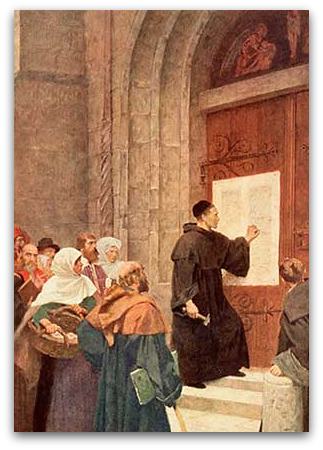
2025年10月26日(日) 説教
宗教改革主日
ヨハネによる福音書8章31~36節
留まるべきところ
本日の福音書の初めには、「イエスは、ご自分を信じたユダヤ人たちに言われた。『私の言葉にとどまるならば、あなたがたは本当に私の弟子である』」というふうに記されていました。
イエスは、ご自分を信じたユダヤ人たちにものを言っておられます。ここで「ご自分を信じたユダヤ人たち」とは、すぐ前の30節に書かれている、「これらのことを語られたとき、多くの人がイエスを信じた」、その人たちのことです。
ところが、そのやり取りを見てみますと、信じた人たちの心の変化が激しく変わっていることに気づかされます。37節では、「だが、あなたがたは私を殺そうとしている」と述べておられ、40節でも「この私を殺そうとしている」というイエスさまの言葉があります。非常に物騒な雲動きができているように見えるのです。確かに初めは「信じた人々」に話していたのですが、どこか途中から相手が変わってしまって、むしろイエスを「殺そうとしている」敵に向かって話をなさっているようになっています。つまり、信じた人たちが殺す人に変わっていく、そのスイッチの切り替えはどこにあったのでしょうか。
日本語の訳だとわかりにくいところがありますが、31節で「イエスを信じた」と書かれているところの「信じた」という言葉は、信じてずっと信じ続けたというニュアンスの言葉ではありません。そうではなく、ある特定のときに信じたという、一時的に「信じた」、イエスの話を聞いたその時点では、確かに納得し感心して「信じた」けれども、今はそうではないというニュアンスの言葉です。ですから、ここでイエスが話の相手に選んでおられる「イエスを信じた人々」とは、そうではなくて、あるとき信仰をもっただけで、今はあやふやになっている、あるいは敵側に回るかもしれないような、中途半端な、本当の弟子になり切るまでの途中の人たちだったということになります。
特にヨハネ福音書のイエスのメッセージは、とどまることを強調しています。15章では、ぶどうの木をご自分にたとえ、ご自分に従う人々のことをその枝としてたとえておられます。「私につながっていなさい。私もあなたがたにつながっている。ぶどうの枝が、木につながっていなければ、自分では実を結ぶことができないように、あなたがたも、私につながっていなければ、実を結ぶことができない」(15:4)と。つながっていることの大切さが述べられています。
それは、ヨハネ共同体が置かれた状況を表していることでもあります。
ヨハネ共同体が活動していた時代、かれらはローマ帝国による迫害と、キリスト教徒を異端と見なすユダヤ教共同体からの迫害という、二重の苦難に直面していました。外からの二重の迫害に耐えるためには、仲間が一致団結していなければ立ち向かうことが難しくなります。一本のぶどうの木にすべての枝がつながって、一本の木から栄養をもらって元気に養われて実を結ぶ。つまり、イエスの木につながっていることで、攻めてくる外の敵に立ち向かう力を養えるということです。
他の箇所では、互いに愛し合うことが勧められていますが、それも同じことです。「互いに愛し合いなさい。私があなたがたを愛したように、あなたがたも互いに愛し合いなさい。互いに愛し合うならば、それによってあなたがたが私の弟子であることを、皆が知るであろう」(13:34~35)と。とどまることとつながること、愛し合うことは同じことです。
しかしながら、そういう大切なメッセージを発する共同体の中にも、信仰への確信が持てず疑う人がいて、裏切る者が現れる。信じたつもりで従い始めたのに信じ切れず挫折する場合があるのです。しかし、それはおかしなことではなく、人間の持てる性質がそうなのだと思うのです。人は、人形やロボットではないからです。生身の者ですから、心は刺激を受ければ変化しますし、それと思うものに惑わされて葛藤します。それは、今の私たちも日々の歩みの中で経験していることです。洗礼を受けた頃のことを思い起こしてもいいかもしれません。イエス・キリストを私の救い主として受け入れ、一生涯この方について行きますと告白をして洗礼を受けても、時が経つにつれて熱さが覚めてくると、だんだんと信仰が薄くなっていく。しかし、そういうことの繰り返しの中で私たちの信仰は培われていくのだと思うのです。
問題なのは、洗礼を受けてとても熱心に奉仕をし、命までささげて従いますとまではいかなくても、一所懸命に仕えていた人が、何かのときに、自分の思いが通らなくなると、疑い始め、教会や牧師を批判して教会から出て行く場合があります。その場合、とても困ってしまいます。何度かそういう経験をしていますが、その度、戸惑ってしまいます。
今日の福音書でも、イエスの教えを受け入れてイエスを信じた人々の中にもそういう人たちがいて、イエスも困っていらっしゃるようです。その人たちは、いっそう、イエスを殺す側に立つほど、信じる喜びが敵意に変わってしまったのでした。もちろん、スイッチが入れ替わるそこには、自分なりの理由があるのでしょう。イエスに嫉妬し、敵意を持っているユダヤ人のグループからの刺激があったのかもしれません。
ですから、惑わされないように、「私の言葉にとどまりなさい」「私の本当の弟子になりたいのなら、御言葉に私の言葉にとどまることだ」と、イエスさまは呼び掛けておられるわけです。なぜなら、敵意をもって生きることは、かなり不自由なことだからです。誰かに憎しみの感情を持ち続けることがどれだけの体力を損なわせることかわかりません。精神的にも大変です。病に侵される危険さえあります。悪の奴隷状態ですから、暗闇の鎖の中に監禁されているような状態です。
今日はマルティン・ルターの宗教改革を記念する日ですが、ルターの時代も同じく、イエスの言葉から離れ、その教えの反対側に立ち、人々を惑わせ、どんどん暗闇の中に導く人たちがいました。特に、教会の指導者たちです。救われるためには免罪符というチケットが必要であると。当時、自分で聖書を読めず、教会の指導者たちの教えだけが唯一神への通路だった人々は、死んだ家族分まで免罪符を買うことで神の救いをゲットしようとしていたのでした。神の救いが売買されていたのです。
それに対して、ルターは、人が救われるのは、善い行いや儀式ではなく、信仰だけである。人は信じることによって義と認められるという福音をローマの信徒への手紙から見つけたのでした。そして、『我ここに立つ』と、当時の神の救いを売買して腐敗した教会に立ち向かったのでした。『我ここに立つ』、「私は御言葉に立つ」、「私は、イエス・キリストの十字架の言葉にのみ立つ」と宣言したのです。
信じる人はその信仰によって救われる。イエスさまは、福音書の中で、人の病気を癒しては、「あなたの信仰があなたを救った」とおっしゃって、その人の信仰をたたえてくださいました。神の力は先行しているけれども、受け入れる側の信仰なしに神の恵みは実現しないのです。私が、私の病気が治ることを信じる、私にはできると信じるときに、先行する神の恵みと私の信仰が一つになって実を結ぶようになります。信じること、つまり、とどまるということ。イエスの言葉を受け入れ、それにとどまる。それが信じるということなのです。
今日、イエスさまは「私の言葉にとどまりなさい」と勧めておられます。私たちのほとんどは聖書を持っていますし、自分で、日本語で聖書を読めます。ですから、読んですぐ意味が分からなくても、毎日一章ずつでも聖書を読んで黙想をするのです。それは、聖書日課に決められているところを読んでもいいのです。聖書を読む時間を一日のルーティンの中に入れましょう。ある方は、朝、まず聖書を読まなければご飯を食べない、ご飯が食べたいから聖書を読むのだとおっしゃっておられました。それでいいのです。一日のルーティンの中に聖書を読む時間を入れていれば、嫌でも御言葉に触れることになります。御言葉にとどまることがイエスの中にとどまることになり、そのとき、私たちは本当の意味の、内面の自由を生きることができるのでしょう。内面が自由で、あらゆる壁を越えている人のことを、イエスは、「ご自分の弟子」と言ってくださっているのではないでしょうか。
Youtubeもご視聴下さい。