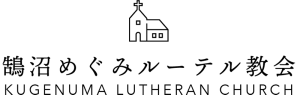関係性の回復
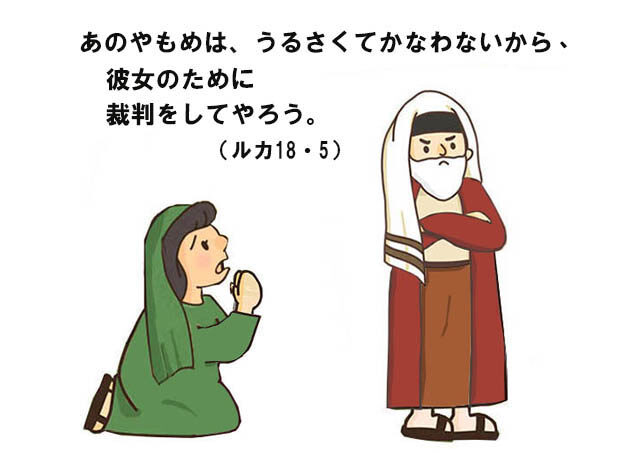
2025年10月19日(日) 説教
聖霊降臨後第19主日
ルカによる福音書18章1~8節、創世記32章23~32節
関係性の回復
今日の福音書は、どんなときも落胆しないで祈ることを勧めています。そのためにイエスさまは、一つのたとえ話を話してくださいました。一人のやもめが、「神を畏れず人を人とも思わない裁判官」を訪ね、自分が不当な扱いを受けていることを訴えています。当時、やもめは社会的弱者であり、律法の保護を受けなければ生きることが難しい立場にありました。イスラエルのみならず、日本や韓国も昔はやもめの生きる道が男性を通してしかなかったのです。生まれては父親の保護の下で育ち、結婚したら夫の者とされ、夫に先立たれたら息子の保護下で生きる道しかなかったのです。息子もいなく一人残された場合はとても大変で、そのやもめたちを守るための律法がちゃんとできていたのです。ですから、やもめが訴えることは優先されなければいけないことになっていました。しかし、当時の宗教界は、やもめのような弱い立場に置かれた人たちに対して、果たすべき役割を果たしていなかったのです。
イエスさまは、他のところで、当時の教会や教会の指導者たちに対して厳しく言われます。
「『律法学者に注意しなさい。彼らは正装して歩きたがり、また、広場で挨拶されること、会堂では上席、宴会では上座に座ることを好む。また、やもめの家を食い物にし、見せかけの長い祈りをする。このような者たちは、人一倍厳しい裁きを受けることになる。』」(ルカ20:46∸47)。
もしかしたら、本日のやもめは、宗教界の指導者たちに利用され、財産が奪われ、人権を無視されるような、不当な扱いを受けていたのかもしれません。
しかし、イエスさまは、たとえそうであって、どんなにひどい扱いを受けて、何もかも奪われてしまったとしても、落胆しないで、気を落とさずに祈りなさい。祈り続ければ、その祈りは必ず神さまに聞き入れられると勧めておられます。
ここで聞きたいのですが、なぜ、イエスさまは、他でもなくやもめをたとえ話の中に登場させたのでしょうか。信仰的に敬虔な生き方をしていて素晴らしい実践を行っている人や、祈りを大切にしている人を通して話されてもよかったと思うのですが、やもめを祈る人の中心においておられるのです。
その答えは旧約聖書の時代から大切に伝えられているところにあります。
出エジプト記22章には、「いかなる寡婦も孤児も苦しめてはならない。あなたが彼らをひどく苦しめ、彼らが私にしきりに叫ぶなら、私は必ずその叫びを聞く」(21‐22)と記され、申命記10章には、「あなたがたの神、主は神の中の神、主の中の主、偉大で勇ましい畏るべき神、偏り見ることも、賄賂を取ることもなく、孤児と寡婦の権利を守り、寄留者を愛してパンと衣服を与えられる方である。」(17‐18)と記されています。
寡婦、つまりやもめと一緒に家族がいない孤児と故郷を離れて寄留する人たちが記されていますが、孤児や寄留者も自分の力だけでは生きてくことが難しい、弱い立場に置かれた人たちでした。ですから、大切なのは、神さまがこの人たちの味方でおられるということです。神さまは常にこの人たちの立場にたち、この人たちの必要に心を動かし、その権利を守られると宣言しておられるのです。これが旧約聖書の時代から大切に伝えられてきたことでした。
ですから、神に仕えて生きるということは、孤児ややもめ、寄留する人たちの権利を守ること、必要を知り分かち合うこと、教会の群れの中にこの人たちの居場所を作るということでした。
しかし、もし、そういうことが守られず、やもめたちが不当な扱いを受けて叫ぶ場合、神さまは、その叫び声に直ちに応答なさるというのです。やもめの権利や財産を奪い取る者たちの行いを裁かれるということ。神さまがやもめの背後に立って味方しておられる!つまり、叫び求める祈りが直ちに聞かれる人、やもめ、それゆえ、イエスさまは、絶えず、落胆せず祈り続ける人の模範を、やもめを通して示されたのでした。
日の福音書で、神さまを味方にして必死に訴えるやもめ、その相手は、「神を畏れず人を人とも思わない裁判官」です。もちろん、彼は、神さまがやもめの味方をしておられることなど知りません。彼は、神を畏れない人でした。さらには、「人を人とも思わない」人ということですから、やもめのように社会的弱者の立場に置かれている人は、彼の蔑視の対象になっていたのかもしれません。それは、彼が、裁判官でありながら、依然としてやもめの訴えを取り上げようとしないことからも十分察することができます。
しかし、最終的に、彼は、やもめの訴えを取り上げようとします。それは、やもめが置かれた状況を同情するとか、憐れむような温かい思いからではなく、やもめがあまりにも執拗に訴えるために、うるさいから取り上げようとしたということです。あくまでも自己中心的な思いでした。
この物語は、私たちに、落胆しないで祈り続けることを勧めると同時に、他に伝えようとしていることがあることに気づきます。
私たちの生きる社会や教会は、このやもめが置かれたような、一方的に不当な扱いを受けるほど、大変な社会ではありません。日本国民として、「自由権」、「平等権」「社会権」という三大権利がちゃんと守られていますし、生活保護法に基づいて、基本的生活が守られる環境の中で暮らしています。財産の分け方や雇用主との間に問題が生じた場合は、法律に基づいて解決できる社会です。そういう国や社会状況の中で生きる私たちは、今日のやもめと裁判官のやり取りをどのように受け止めたらいいのでしょうか。このやもめほど、不当な扱いを受け、権利を奪われるほど、必死に訴えなければならない祈りの課題がない。ですから、このたとえ話を他人事のようにしか受け止められない側面が強いのではないでしょうか。
もし、私たちが、本当に川向こうの火事のようにしかこのやもめと向き合っていないのなら、私たちは、「神を畏れず人を人とも思わない裁判官」と同じ人間だということになります。生きるためのほとんどのものが整えられていて、それほど欠如を感じない。むしろ、有り余っていて、断捨離だ、終活だと言って、あるものをなくすために困っているのです。国の法律から守られていて、男女関係なく働く場が与えられていますし、経済的にも、貧しい国々に比べれば十分豊かな暮らしをしています。
つまりそれは、神を畏れ神に訪ねなくても、自分の力で生きていけるということです。自分の生活が豊かなときに、人はあまり神により頼まなければ、人の欠如に気づこうとしません。社会的に弱い立場にいる人がすぐ隣に住んでいても、その人は私にとってよそ者、知らない人なのです。やもめに限らず、故郷を追われて入ってくる寄留者、つまり、難民の人々。最近、外国人を受け入れないという雰囲気が造られつつありますが、外国人は日本から出て行けということを聞くとき、私は出て行かなければならないのかと、自分の居場所が狭くなってくるような気がして悲しいです。
または、性的マイノリティの中に置かれている人々。ある方は、性的マイノリティの中に置かれた人たちに対して、嫌悪感さえ抱いてしまうと言っていました。出会ったこともないのに、先入観の支配を受けているからでしょう。
神を愛し、隣人を自分のように愛しなさいというイエスさまの戒めをよく知っている私たち、私たちの教会の扉はどこに向かって開いているのでしょうか。この教会を自分たちだけのものとし、変わった人は入って来ないように固く閉ざしてしまっているのではないでしょうか。「神を畏れず人を人とも思わない裁判官」は、社会的弱者に対して閉ざされた人でした。それゆえ、神に対しても心を開くことは出来なかったのです。その人がしきりに訴えるやもめによって心が動かされているのです。
私たちの教会が、今日のイエスさまのたとえ話に耳を傾けて、弱い立場に置かれた人々に対して扉を開こうとすれば、きっと、奪われた権利を取り戻すために必死に訴えて祈るやもめの祈りが聞こえることでしょう。そして、その祈りが聞こえたときに初めて私たちはすべての扉を開いて、この場を神ご自身がご自由に働かれる宣教の場として差し出すようになるのではないでしょうか。神を神として畏れ敬い、人を人として尊重する人の心に、イエス・キリストが担われた十字架が立ちます。神さまと人との、縦と横の関係が自分の中に成り立つときに、私たちは、自分の思い上がりを神に委ね、最も弱い立場に置かれたやもめのような人によって、自分が神に支えられていることに気づかされるのではないでしょうか。
Youtubeもご視聴下さい。