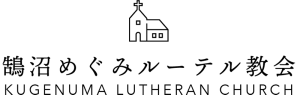招かれる幸い

2025年8月31日(日) 説教
ルカによる福音書14章1節、7~14節
招かれる幸い
8月も今日一日だけ残りました。暑かったし、まさに今日暑さがピークになりました。みなさんはどんな風に8月を過ごされましたか。
8月は、幼稚園が夏休みで、教会の平日の集会もすべて休みなので時間がたっぷりあるようで、他のスケジュールがいろいろと入ってきます。毎年8月に行われる関東地区青年会のサマーキャンプが今年も行われました。帰省してお墓参りに行ったり、懐かしい方々に会ったり、遠くに住んでいる家族を迎えたり、皆さんもいつもとは違う日常をお過ごしになったのではないでしょうか。
非日常的なスケジュールが一か月も続くと疲れてくる面もありますが、普段は味わえないものがあります。思いがけない人に出会ったり、新しい気づきが与えられたり、さらには、それが将来の希望へとつながる。新しい出会いが将来の希望を産み出してくれるのです。ですから、8月は、出会いの季節と言ってもいいかもしれません。そしてその出会いが平和の道につながります。なぜなら、真の平和は一人歩きするものではないからです。私が誰かと出会う、全く知らない人とつながっていく、そういうことによってこそ真の平和は造り上げられるからです。私たちがどんどん新しい出会いを果たしていれば、世界から戦争がなくなることでしょう。そういう意味では、暑いこの8月がもっと続いていいかもしれませんが、出会った関係を育んでいくためには涼しさも必要と思いますから、残された最後の一日を大切に送りたいと思います。
先ほど読まれた福音書で、イエスさまも食事会に招かれ、そこでいろいろな人と出会っていらっしゃいます。招いた人の名前はなく、ファリサイ派のある議員とだけ記されています。ファリサイ派の議員の人の家ですから、招かれた客のほとんどは議員の仲間たちでしょう。宗教界や社会のエリートと言える人たちが招かれた、その席にイエスさまもご一緒です。
しかし、イエスさまはその宴会の客ぶれがご自分の好みではなかったようです。イエスさまは、早速、招いてくれた議員にこのようにお勧めしておられます。
「昼食や夕食の会を催すときには、友人も、兄弟も、親類も、近所の金持ちも呼んではならない。… 宴会を催すときには、貧しい人、体の不自由な人、足の不自由な人、目の見えない人を招きなさい。そうすれば、彼らはお返しができないから、あなたは幸いな者となる。」(12∸14)。
今日、私たちは、「平和」をテーマに音楽礼拝を守っていますが、このイエスさまのお勧めの言葉を中心に「平和」についての福音を分かち合いたいと思います。
「宴会を催すときには」。「宴会」は、喜びを分かち合う場です。イエスさまもご一緒におられるこの日は、主の日、安息日でした。安息日をお祝いし、喜びを分かち合うためにみなさんは招かれています。
私たちも、時々、折に触れて、客を招いて食卓を囲みます。私も、この8月に、教会のある方のお家にお招きを受けて、交わりの場に与らせていただきました。久しぶりに会った仲間やいつも顔を合わせる仲間たちと楽しいときを過ごしました。招きを受けることは嬉しいことです。私も時々牧師館に人を招きますが、招く側も嬉しい気持ちになります。招いて、招かれる。聖書はそのことを勧めますし、キリスト教の長い伝統の中でも大切なこととして受け継がれてきました。
しかしイエスさまは、「宴会を催すときには、貧しい人、体の不自由な人、足の不自由な人、目の見えない人を招きなさい」と勧めておられる。
いっぺん難しいことのように思います。見知らぬ人を招くようにというお勧めだからです。しかし、イエスさまがリストに上げているこの人々は、どういう人のことか。もう少し考える必要があります。
私がまだ大宮教会で牧会をしていた時のことです。高校3年生の息子が進路を決める時期になって、三者面談に呼ばれました。そのとき、担任の先生から、アメリカの大学に進むようにと勧められました。アメリカの田舎の大学に入れば、かかるお金は、日本の私立大学に入ったのとあまり変わらないし、特にこの子はお母さんから遠く離した方がいいと。それで、アメリカの大学行きを準備し始めたのです。しかし、息子が選んだのは田舎ではなく、サンフランシスコの周辺にある学校で、学費はそれほど高くないのですが、生活費が学費の何倍も高くかかる地域でした。どう考えても私の収入と息子にかかるお金の割合が合わない。それで私は毎日悩み、心は不安でいっぱいになりました。
それで、ある主日の礼拝の派遣の歌のときです。私の胸にお言葉が臨みました。「あなたが支えなさい。あの子は、アメリカに行けば、手もなく、足もない、孤児だから」と。
胸に臨んだこの言葉で、私は、歌うことも出来ず、ひたすら泣きました。神さまが動き始めた!それなら何とかなる!という確信と、それまで神さまに委ねられなかった自分の愚かに気づかされ、心の中の不安は平安に変わり、限りない自由が広がりました。一曲の讃美歌が歌われる短い時の中でしたが、神さまと交わった時間は、時空を遥かに超えて別世界に行ってきたと思うほど、とても深く、広い世界の交わりでした。
もちろん、息子は手もあり足もあります。孤児でもありません。しかし、手と足があっても自分で稼ぐことが出来ず、日本を離れれば孤児同然なものです。
つまりそれは、私たちも、五体が健康でも、一人で自由に動けず人の助けを必要とする場合があるということです。そうなれば、誰かに手となり足となって支えられなければならない。または、一人で動けるとしても、自分一人よがりの働き方をしていれば、狭い井戸の中をぐるぐると回っているようなものに過ぎなくなる。誰かにささえられながら、または、誰かの手となり足となってつながることによって、それによってこそ私たちは自分らしく生きることができる、ということです。
ここに、十字架と復活の神理解があります。私たちが、十字架につけられて動けなくなったイエスさまの手となり足となる、そういう生き方をしていくときに、死んだイエスさまが私たちを通して復活なさるのです。私たちの手と足を隣人のために用いていくときに、私たちは復活の信仰を生きる者になります。こういう具体的な生き方の中で、私たちに、新しい気づきが与えられ、それまでは見えなかった道が見えるようになり、新しい視点が開かれます。そうやって、私たちが、どんどん外へ向けて心の扉を開いていけば、世界とつながり、世界の平和を司る者になっていくのです。
私の手や足もよろよろしているのに人を支えることなどできないと考えてはなりません。体が弱くなっても、祈りをもって、または経済的力を用いて、さらには、暖かい言葉や笑顔が、人の手となり足となる働きになります。
今、ガザ地区が孤立して、酷い飢饉の中に置かれています。子どもたちが栄養失調で死につつある。アフリカの諸国よりも酷い状態であると報じられています。胸が痛いです。誰が死にゆくこの子どもたちに食べるものを届けるのでしょうか。それは、私たちです。もちろん、直接行くことは難しいです。関わっている団体を通して支えることになりますが、酷い状況に追いやられている人々と私たちが連帯するのです。それによって、ガザ地区の人々の必要が届けられる道は開きます。私がしなければその道は閉ざされたままになります。
ガザ地区の人々を私たちの食卓に招き、私たちの交わりの中に、この礼拝の中に招くことで、一人でも命を失わずに生きる道が拓かれます。
つまり、人を孤立させない。私たちの豊かさから、小ささくされている人々を追い出さない。もしかしたら、この鵠沼にも、経済的には豊かでも孤立されている人がいるかもしれません。
踏み入って考えれば、イエスさまがリストに上げている「貧しい人、体の不自由な人、足の不自由な人、目の見えない人」は、つまり、私自身のことであるということ。自分一人では、今日も、このように神さまに招かれ、神の国の福音の食卓に与り、魂の渇きが癒されていることにも気づくことなく、感謝することの乏しい、この私のことであるということです。その私たちを、今、神さまは、ご自分の食卓にお招きくださいました。そして、たくさん食べなさい、遠慮することなく飲みなさい、満腹になって、孤立されて一人歩きできないあなたの隣人のところへ遣わされなさい、と。神さまは私たちをご自分を現す器として遣わせてくださっています。恐れることはありません。喜んで遣わされてゆきましょう。
Youtubeもご視聴下さい。