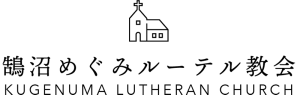木を植えた人
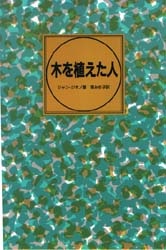
2025年7月13日(日) 説教
聖霊降臨後第5主日
ルカによる福音書10章25~37節
木を植えた人
ジャン・ジオノの「木を植えた人」という本を読んだことがありますでしょうか。
七十年も経っていますが、未だに読まれている本です。
一人の男が荒廃して捨てられた地に木を植え続けます。そこは、人々に住み捨てられ、期待されない地でした。その地に、毎日木を植え続ける人。木を植えることで自分に返ってくる利益があるわけもなく、人々の評価もありません。奥まったところですから、彼がやっていることを誰も知らないのです。木を植える人は、ただその地に合う木の種類だけを調べ、黙々とその種を土の中に植えます。食べる物は質素で、言葉数も少なく、人がいてもほとんど沈黙のうちに過ごします。しかし、信じた道を諦めず歩き続ける。植えた種が芽を出すのは三分の一くらい。それでも失望せず植えることを止めません。ときは第一・二世界大戦のときで、戦争の噂にも迷わされることはありません。こんな時代に木を植えて何になるとか、今自分がやっていることにどんな意味があるかなど考えません。
その結果、荒廃地だったところは森となり、水が流れ、鳥たちが来て巣を作って子どもを産み、花々も咲くような楽園になりました。権力者は戦争を起こして世界を変えようとし、経済を重んじる人は経済成長を通して世界を変えようとします。その結果、世界は変わりましたが、人々が住みにくい世界になりました。しかし、権力者も経済成長もできなかったことを、木を植え続けた人は成し遂げました。神さまが造られた美しい世界を再現し、命あるものが自由に来て住める場所を作ったのです。
今年の夏も私たちは猛暑に見舞われています。温暖化の影響で季節の感覚が狂ってしまいました。鹿児島の付近では地震活動が活発に行われ、人々が余儀なく避難生活を強いられています。環境問題がますます深刻になってきました。これは、経済成長を重んじる政策の結果です。
さらには、絶えず知らされる戦争のニュース。そのために被害に遭っている人々の状況を聞くたびに悲しい思いでいっぱいです。けれども、どうしたらいいかわからない、私一人で何ができる?自分一人ががんばることにどんな意味がある?と思い、世界の各地で起きている悲しいことを、私たちは他人事のように受け止めている面もあるのではないでしょうか。そういう思いが私たちの心の扉を閉ざし、私さえよければいい、私の家族や親しい人たちが守られればいいという、隣人が欠如した世界をつくり、自分の中に閉じこもっていく生き方を選び取ってしまいます。
先ほど拝読された福音書の中で、永遠のいのちを受け継ぎたいという思いをもってイエスを訪れた律法の専門家もそういう中の一人でした。律法の専門家というと、社会的地位もあり、生活に困ることもなく、一緒に働く仲間もいて、社会や教会で尊敬される立場にいます。しかし、彼の魂は渇き果てていた。尊敬されているとしても、渇いた魂を癒すのに、自分が持っているものは何の役にも立たない。その彼にイエスは、良きサマリア人のことをたとえ話として聞かせました。
ある人が旅の途中追いはぎに合い、持ち物もすべて取られ、半殺し状態で道に倒れていた。そこを祭司やレビ人が通るが、彼らは、関わらないようにし、遠回りして行ってしまった。しかし、旅をしていたサマリア人は、倒れている人を見るや否や、傷に手当てをして、自分の家畜に乗せて宿屋に連れてゆき、介抱をした。さらには、次の日、出かける際に、かかるすべての費用は自分が支払うと言って宿屋に介抱をお願いした。
お話を終えられたイエスさまは律法の専門家に聞きます。「この中で、追いはぎにあった人の隣人は誰なのか」と。すると律法の専門家は、「彼に憐みを施した人です」と答えます。私は、彼の答えの中に深い悲しみを察します。祭司やレビ人は彼の仕事の仲間たちです。その仲間を否定せざるを得ない。その彼にイエスさまは勧めます。「行って、あなたも同じようにしなさい」と。
「何をしたら永遠の命を受け継ぐことができるでしょうか」と、何か自分の能力を発揮して永遠の命を手に入れようとしていたこの律法の専門家は、サマリア人と同じことをするように勧められました。つまり、永遠の命を受け継ぐ方法は、サマリア人が倒れている人のところに出かけて行ったように出かけていくこと、自分から他者へ、困っている人へ、憐れむ心をもって出かけていくということ。その中に永遠の命を受け継ぐ秘訣はあると言うことです。
当時、サマリア人とユダヤ人が敵対し合い、ユダヤ人はサマリア人を汚れた民族として軽蔑していました。そういうただ中で、イエスさまは喩え話の中でサマリア人を立てています。果たして、この律法の専門家はイエスさまのお勧めを生きる人になったのでしょうか。サマリア人とユダヤ人は等しく神さまに愛され、同じく救われているということを、その生き方の中にあらわす人になったのでしょうか。もし、そうなったとしたら、彼はどのようにして具体的な実践を生きる人になったのでしょうか。
私たちはどうでしょうか。律法の専門家が言うように、「心を尽くし、魂を尽くし、力を尽くし、思いを尽くして神を愛し、隣人を自分のように愛する」と勧める聖書の言葉は知っていても、お言葉とおり実践できない自分の弱さに嘆いてばかりしていないでしょうか。この律法の専門家も自分の限界にぶつかっていたのでしょう。神を愛し人を愛するということを、知ってはいるものの実践に移すことの難しさ。仕事仲間の中にも相性が合わず受け入れがたい人がいて悩んでいたのかもしれません。仲良くしたいのにできない。他民族を汚れているとして自分との間に壁を立てている偏見的心と愛することの間の矛盾、人を分け隔てる自分が神さまに見捨てられているようで不安な日々。しかし、プライドがあるのでその心を外に出すのは顔がつぶれる思いがしてできない。それでイエスさまを訪れたのです。
プライドを捨てない限り、人は、神に出会うことも、人に出会うこともできません。プライドを持って生きることは、欲望を膨らんでいるほかなのです。
「木を植えた人」を書いた作家ジャン・ジオノはフランス生まれで、もとの職業は銀行マンでした。ところが、徴兵されて戦場へ行き、たくさんの人の死を目撃し、彼は片目を失います。そのときから彼は平和主義者になります。彼が書くものすべては平和に関するもので、人の内面と大自然と調和する物語ばかりです。
彼が書いた「木を植えた人」は、お父さんがモデルになっています。自分を連れて、荒廃した地にどんぐりの種をもくもくと植え続けるお父さんの姿。若かった彼に、そのお父さんの姿はばかばかしく映っていた。それから、徴兵され、五年後に帰ったとき、作者の目に映ったのは、巨大な森に化していました。一人の人の努力、その誠実さ、信じる心、それが、荒れ野を森に、死んでいた地を命が宿る地に変えたのでした。愚かな生き方にしか見えなかった人の素朴な歩みが、神さまの創造の秩序が取り戻し、死んだ場所を命が宿る美しい世界に変えたのでした。まさに、復活です。
自分の信じた道を歩むということ。私には木を植え続けた人がイエスさまのように見えました。イエスさまも、ご自分が信じた道を歩み続けました。それは、イエスさまの中に何の能力がなかったからではなく、自分の中の能力を使って独りよがりの生き方こそ神の御心に反することだと言うことを知っておられたからです。ですから、イエスさまは常に人のところへ出かけて行き、人の弱さと結び合い、そこで共に生きることを神の御心が示す道であると信じたのです。
イエスさまは私たちにそういう歩みを勧めておられます。自分の信じた道を歩みなさい。人々の評価や言葉に左右されず、神さまとの関係の中で示された信頼の道を歩きなさい。そもそも「その信頼の道が分りません」という方がおられるかもしれません。それは、イエスさまのように生きることです。何かをやっていても何もしないときでも、人と自分を比較しないこと。人が下す評価を恐れないこと。さらには、人の弱さを憐れむ心をもって支えること。なぜなら、神さまは、私たち一人ひとりを人と比較することもなく、私たちが何か良いことをしたことによって評価するのでもなく、私たちの弱さを愛し、その中に宿られてそっと寄り添って、愛してくださる、その愛を先立って示してくださっているからです。
今日も、神さまは隣人の姿を通して私たちと一緒におられます。子どもたちの姿、友だちの姿、親や兄弟姉妹、学校や会社の仲間、道を通る知らない人の姿、私を苦しめる人の姿をして寄り添っておられるかもしれない。その隣人を通して神さまは私の荒廃した心の畑に命の種を植えながら一緒におられます。
Youtubeもご視聴下さい。