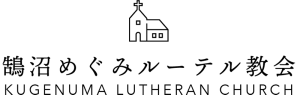互いに重荷を担い合う

2025年7月6日(日) 説教
聖霊降臨後第4主日
ルカによる福音書10章1~11,16~20節
互いに重荷を担い合う
この頃、毎朝一時間歩くようにしていますが、歩くコースの中に鵠沼海岸が入っています。朝の海岸はとてもさわやかで気持ちがよく、押し寄せる波の音や足に当たる感覚の柔らかさにとても慰められます。訪れるたびに新しい光景に出会うので、今日はどんなことに出遭えるのだろうと楽しみになります。
ある日の朝でした。小さなイカが打ち上げられていました。他の魚が打ち上げられているのはよく見ていましたが、イカを見たのは初めてでした。小さかったのでかわいそうにと思いしばらくその場にとどまって思いました。海の中で何があったのだろう。前の晩は雷がなって空が荒れていたので、きっと海の中もその影響を受けたのかもしれない。家族とはぐれてしまって、海の中の家族が探しているのかもしれない。しかし、もう帰れない。
そう考えているうちに、故郷を離れた人のこと、難民のことにまで思いをはせるようになりました。今、このときも、辿りつく場所を探せないまま海の上を漂っている人たちがいる。海の上で守られますように、辿りつく場所が見つかりますようにと祈りながらその場を離れました。
他の日の朝、その日は引潮で海がずっと引いていて、歩けるところがとても広くなっていました。その上を歩いていると、まるで自分が海の中を歩いているように思えて、海の中のことを想像していました。小さな魚たちが私の足音を聞いて驚いて岩の後ろに隠れる様子、群がっていたのが私のせいで散り散りになっていると思うと、申し訳ない気持ちと、でももっと魚たちと遊びたい気持ちで、砂の上と海の中とが一つになって楽しい時間でした。こうして毎朝毎朝海岸で力をいただいているのです。自然界は大きな力をもっています。鵠沼海岸はパワースポットだと思いますから、行かれる方は朝の早い時間帯に行ってみてください。
さて、今日、イエスさまは七十二名を任命し、ご自分が行こうとする町や村に派遣しておられます。イエスさまの弟子の数がいつの間にか増えています。これまでは、9章に十二使徒の派遣が記されていましたが、ほんのわずかな時間しか経過していないのに、派遣される弟子の数が六倍も増えています。きっとこれは、イエスの宣教が本格的に始まったということをあらわしているのでしょう。
イエスに任命された七十二名の弟子たち。彼らは、二人ずつ遣わされています。二人組で派遣することは、きっとイエスさまのやり方だったと思うのですが、このやり方は、イエスさまが昇天なさった後の使徒たちの時代にも守られました。ペトロとヨハネは常に二人で動いていますし、パウロも伝道に出かけるときには必ず誰かと一緒です。これはとても大切なことです。たとえば、法廷に証人として立たされるとき、一人の証言よりは二人の証言が確実になるように、福音を述べ伝えるときもそうです。「神の国があなたがたに近づいた」という福音を、一人が述べるときよりも、二人が述べるときにより多くの人が耳を傾けるのです。
私も、信徒の方を訪問するとき、一人ではなく二人で行くようにしています。ずっと昔から一緒に信仰生活を送ってこられた仲間と話す方が話しやすいと思うからです。それに私にとって、どなたかが一緒に行ってくださることは大きな助けになります。このことは、信徒訪問のときだけでなく、日曜日に私がほかの教会に手伝いに行くときも同じです。教会同士の信徒の交わりにもつながると思うので、どなたか一緒に行きませんか。
さて、イエスさまは、十二使徒を派遣する際に弟子たちにその心得を厳しく伝えられましたが、今日、七十二名の派遣においても、心得ておくべきことを告げておられます。
すなわち、収穫は多いが働き手が少ない。だから、収穫のために働き手を送ってくださるように願うこと。財布も袋も履物も持って行かないこと。誰とも道で挨拶をしないこと。迎えられた家に泊まって、そこで出されるものを食べて飲むこと。家から家へと渡り歩かないこと。どんな家に入っても、先ず「この家に平和があるように」と言うこと。その町の病人を癒し、「神の国はあなたがたに近づいた」と告げること。町に入っても迎え入れられなければ、「足についたこの町の埃さえも払い落として、あなたがたに返す。しかし、神の国が近づいたことは知っておけ」と言うこと。
これらの中で最初に勧められた、「収穫は多いが働き手が少ない。だから、収穫のために働き手を送ってくださるように願うこと」について分かち合いたいと思います。この言葉のすぐ後に、「行きなさい。私があなたがたを遣わすのは、狼の中に小羊を送り込むようなものである」という言葉が続きます。これは、多くの実りを刈り取ることを躊躇するな、邪魔する者もいることでしょう。しかし、私があなたがたと一緒にいるから勇気を出しなさいというメッセージなのです。
使徒言行録18章にはパウロがコリントで働いていたときのことが記されています。ユダヤ人に対して、「メシアはイエスである」とパウロが力強く伝えると、ユダヤ人たちはパウロの言葉を聞こうともしなければ、むしろ口を悪くして罵ります。それでパウロがそこでの宣教を諦めて他へ行こうとしたときの夜、主は幻の中でパウロに言われるのでした。「『恐れるな。語り続けよ。黙っているな。私はあなたと共にいる。だから、あなたを襲って危害を加える者はない。この町には、私の民が大勢いるからだ。』」(9~10)。
 イエスさまが勧めておられるのと同じ状況がパウロの時代にもあったのです。それは、どの時代もあるということでしょう。イエスさまは派遣される弟子たちに勧めておられます。「収穫が多いのだから、がんばってこい」と。「収穫が多い」とは、言うまでもなく刈り入れるものが多いと言うことです。ですから、体がいくつあっても足りないぐらい働かなければならない、休む間もなく忙しい状況です。しかしイエスさまのお勧めは、「だから、収穫のために働き手を送ってくださるように願うように」と。それは、自分一人がんばったら間に合うような働き方をするなということです。
イエスさまが勧めておられるのと同じ状況がパウロの時代にもあったのです。それは、どの時代もあるということでしょう。イエスさまは派遣される弟子たちに勧めておられます。「収穫が多いのだから、がんばってこい」と。「収穫が多い」とは、言うまでもなく刈り入れるものが多いと言うことです。ですから、体がいくつあっても足りないぐらい働かなければならない、休む間もなく忙しい状況です。しかしイエスさまのお勧めは、「だから、収穫のために働き手を送ってくださるように願うように」と。それは、自分一人がんばったら間に合うような働き方をするなということです。
能力のある人は、人に相談せず一人で教会の仕事をこなしてしまいます。しかし、教会の仕事はみんなで担うものです。二人、または三人で話し合って進めていくものです。これはとても大切なことです。神の国の福音を述べ伝えることは、「私ひとり」から「私たち」へと広がる中で実現してゆきます。自分の他にもたくさん働き手が起こされて、手を組み、連帯すること、そのようにして神の国の福音は人々に告げ知らされるのです。ここで言う働き手とは、特別な使命を受けた牧師のような人のことを述べているのではありません。
先ほど読まれた第二朗読のガリラヤの信徒に送る手紙の中でパウロは、「互いに重荷を担い合いなさい」と勧めます。どういうことでしょうか。前後で述べていることからわかるのは、思い上がってはいけない、謙虚でありなさいと言う勧めのように思います。そうです。一人ですべてをやってしまうのではなく、他の誰かと相談しながら協力して一緒に行う。その場合、自分の思うようにいかないこともあります。しかし、本来、宣教とは、特別な使命が与えられて召されている、限られた弟子だけの仕事なのではなく、イエスに従うすべての者のつとめです。
みんなで行うということ。恐れることはありません。私たちが遣わされるところ、そこはイエスさまご自身がご一緒です。七十二名の弟子が遣わされる町や村はイエスさまが行こうとするところでした。同じく、私たちが遣わされる所にもイエスさまが来てくださいます。大切なことは、私たちが福音宣教の最初の一歩を踏み出すかどうか。つまり、話し合う、協力する、連帯するということを通してイエス・キリストを現わそうとするかどうか。
やらなければならないことがたくさんあります。難民をもてなす、神さまがお造りになったこの世界を守るための働き、平和を実現する…しかし、一人で間に合うような働き方を求め、求められている限り、こうした外へ向けての働きはできません。イエスが行こうとする町や村へは行けなくなるのです。教会の宣教をどの方向へ向けていくか、すべては私たち一人ひとりの決断にかかっています。その最初の一歩が踏み出されるなら、私たちの個人的な悩みや恐れ、不安、すべての重荷はイエスさまが一緒に担ってくださいます。
Youtubeもご視聴下さい。