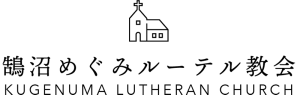人の子には枕する所もない
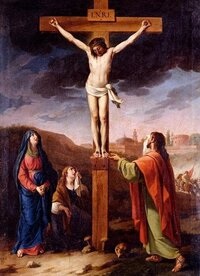
2025年6月29日(日) 説教
聖霊降臨後第3主日
ルカによる福音書9章51~62節
人の子には枕する所もない
枕が変わると眠れないという人がいます。牧師の中にもそういう方がいて、泊まりがけの教職者会などには休みがちです。きっと、旅行に出かけるのも躊躇しておられると思うと、とても残念に思います。
先ほど拝読された聖書の中で、「人の子には枕する所もない」とイエスさまのお言葉がありました。イエスさまも枕が変わると眠れないタイプの方だったのでしょうか。
私は、旅先で、とても安らかに眠れた場所を今でも忘れられません。それは香港の神学校の寮でした。これから10数年前の話ですが、LWFのWICASというアジアの女性たちの集まりが香港の神学校で開かれたときで、私も参加しました。日曜日の礼拝が終わって一人で香港に向かうなか、自分の英語が通じるかどうかがとても不安でした。ところが、空港で乗ったタクシーの運転手さんの言葉は中国語。困りました。プリントアウトしてもっていた紙を見せたら、運転手さんはよく知らない場所のようで、私の不安はますます強くなりました。
本当に私を神学校へ連れて行ってくれるだろうか。どこか他の所に連れて行ってしまったりはしないだろうか…。夜の香港はきれいでしたが、その景色を楽しむ余裕もありません。しかも、神学校に着いたら玄関の扉が閉まっている。運転手さんは何度も電話をかけて、裏門が開いていることを知り、そこへタクシーを回してくれました。そして、日本の女性代表の方が迎えに出てくださいました。そのとき私は、ホッとするのと同時に、この運転手さんがどんなに優しい人で、私のことを心配し、私がちゃんと目的地へ辿りつけるようにしてくださった、建物の中に入るまで私の旅路を守ってくれた人だったということがわかりました。何度も「Thank you!」と言って、運転手さんに感謝しました。
そして、その夜、神学校の寮の部屋に入ってベッドについたとき、言葉では表現できない安らぎが私の心身を包むのです。それは、そのときまで味わったことのない平安でした。もちろん、旅路での不安もあったからそう感じたとも言えます。しかしその場所は、もともとお寺だった所で、長年にわたるお坊さんたちの祈りによって清められ、訪れる人を癒す聖なる器になった。その神学校で学びながら寮生活をしている学生たちがうらやましいと思いました。私にとっては今でも忘れられない場所です。きっとイエスさまも、香港の神学校の寮にいらっしゃれば安心して眠れるのではないでしょうか。
さて、「人の子には枕する所もない」。このイエスさまのお言葉は、「あなたがお出でになる所なら、どこへでも従ってまいります」と言って、弟子の志願を申し立てた人に対してのお答えの言葉でした。その後も二人の弟子志願者がいますが、彼らがこの世的人間関係に延々としている様子をご覧になって、イエスさまは厳しくお声をかけます。つまり、この世で出会った縁に延々とするものは弟子としてふさわしくない、ということです。この厳しさの中には、イエスさまご自身が、「人の子には枕する所もない」とおっしゃるくらい、この世のどこにも、誰にも、何にも、安心して自分を委ねるものはない。それだけ十字架の道の厳しさをあらわしておられます。
そうなのです。イエスさまは、「エルサレムに向かうことを決意された」のでした。それは、エルサレムで迎えるご自分の死を覚悟された、その歩みを始められたということです。その決意ができたならば、それはまっすぐに進むしかありません。そうしますと言って、父を葬りに行かせてください、家族に別れを告げに生かせてくださいと言うのは、「鋤に手をかけてから、後ろを振り返るようなことでしょう。」、「そういう者は、神の国にふさわしくない」と。
私たちはどうでしょうか。イエスの弟子になろうと洗礼を受けて歩み始めて、イエスさまが向かわれるエルサレムへまっすぐに向かっているのでしょうか。
イエスさまはエルサレムに向かうことを決意されました。それはさほど簡単に下せる決意ではなかったはずです。自分の命をささげる道です。一方的にこの世の悪の働きにご自分を委ねる道です。しかし、決意なさった。その一歩としてイエスさまは、人を遣わし、エルサレムへの道を備えさせます。遣わされた人たちはサマリアの村に入りますが、サマリアの人たちはイエスを歓迎しません。なぜなら、「イエスがエルサレムに向かって進んでおられたからである」(53)と。言い換えれば、イエスがユダヤ人であり、他でもなく向かう所がエルサレムだったからというのです。つまり、エルサレムはユダヤ人の巡礼の聖地だからです。サマリア人とユダヤ人の聖地は違っていて、ユダヤ人の聖地はエルサレム、サマリアの人の聖地はゲルジム山という所でした。ヨハネ福音書4章で、イエスさまは礼拝の場所についてサマリアの女と話をしておられます。最初の出発地は一緒だったユダヤ人とサマリア人。しかし、途中で分れて、聖地も異なっています。聖地が異なると、自分たちが巡礼する所こそ神が宿っているという、自分たちこそ正しいと言う思いが互いの中にはあったのでしょう。
韓国には、「いとこが土地を買うとお腹が痛くなる」という言葉があります。いとこ同士はそれだけ難しい関係であることを表しています。親しいようで距離がある。ユダヤ人とサマリア人の関係がそうでした。同じ神を礼拝する宗教や信仰においての違いとなると、そこから生まれる憎悪感は重いものです。イエスさまの時代を遥かに遡って、ユダヤ人とサマリア人の間の敵意感は深かった。そして、何千年が経った今も、その敵対心はますます重くなっていくばかりです。
そうであっても、イエスさまは、ユダヤ人もサマリア人もない。パウロがガラテヤの信徒への手紙で言うように、「キリストにあずかる洗礼を受けたあなたがたは皆、キリストを着たのです。ユダヤ人もギリシア人もありません。奴隷も自由人もありません。男と女もありません。あなたがたは皆、キリスト・イエスにあって一つだからです」(3:27)。神の国では皆が等しく、神の愛の相続人として平等なのだという姿ですべての人と向かい合ってくださいます。
しかし、サマリア人にとってイエスは、ユダヤ人の一人男性としてしか見えていなかった。そもそも、サマリアの村人たちは、巡礼する群れの中におられるイエスがどんな方かを知らないでいたのです。
イエスがどんな方であるかを知らないのは、イエスさまとずっと一緒にいる弟子たちも同じでした。巡礼の準備のために入ったサマリア人の村でノーと断られると、「主よ、お望みなら、天から火を下し、彼らを焼き滅ぼすように言いましょうか」(54節)と、ヤコブとヨハネ兄弟は提案しています。自分たちが正しいと思うことからこういう提案が出てくるのです。
私たちの葛藤や喧嘩のほとんどは、自分が正しいと思うことから始まります。夫婦の間、親子の間、友だちや隣人、国と国の間柄において起こる摩擦は、自分が正しいと思うところからのものです。互いが捉える感覚が異なることを常に考えていれば、世界は平和になることでしょう。実際、互いが向かい合ってみると、相手に見える景色と私に見える景色が異なることがわかります。同じように、テーブルに上がっているものの見え方は、向かい合っている角度が異なるために、違って見えて当たり前なのです。ですから、私にとって正しいことが相手にとっても正しいとは言えません。
イエスと一緒にいる弟子たちも、サマリア人と同じく、イエスが誰で、どんな方であるかを知りませんでした。実は、私たちも同じです。長い間、イエスさまと一緒に生きて来ましたが、イエスとは、ユダヤ人の男性の一人、十字架の上で死んだ人、人類の救い主であるということは知識として知っています。しかし、大切なのは、今、この私にとってイエスはどんな方なのかです。イエスと私の関係をじっくりと吟味しながらしみじみと知らされてゆく。あ、この方は、私のとんでもない弱さの中に枕を置いて休まろうとしておられる方なのだ。私をご自分の癒しの場として用いようとしておられる方である、そのことを知らされる、そういう関係性をイエスさまは求めておられるということです。
きっと、今週も、よそ者の姿をしてイエスさまは私たち一人ひとりを訪れることでしょう。私を感情的にさせ、プライドをつぶすような人の姿をして訪ねてこられるかもしれません。しかし、その方を迎えて、その方が枕を置いて休められる場をつくりたいです。私たちの心の狭いスペースを少し片づけてその方を迎えられれば、そこが神の国になるのです。
Youtubeもご視聴下さい。
今週は音楽礼拝として礼拝を守り、ミャンマー大震災を覚えて祈りました。