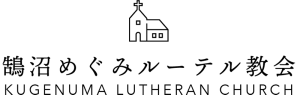変化を受け入れる
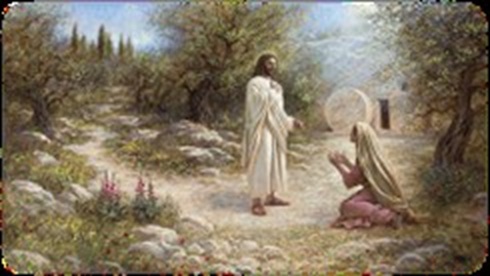
2025年4月20日(日) 説教
主の復活祭
ヨハネによる福音書20章1~18節
変化を受け入れる
キリスト復活! 実に復活! イエス・キリストのご復活、心よりお祝い申し上げます。
復活祭が春に祝われることに改めて感動しています。四季の中で、秋もそうですが、特に春は変化が多い季節です。冬を追い出しながらやってくる春は、大地がひっくり返るほどの変化をもたらします。強風と雨が降り注ぎ、大地から新芽が出て多くのものが育つ季節です。スギやヒノキがまき散らす花粉のために悩まされる人も大勢いますが、春はそれほど変化の多い季節ということでしょう。
イエス・キリストの復活をお祝いする季節がその春であるということ。もちろん、春分の日の次に来る満月に近い日曜日をイースターとして定めるやり方なので春になるのは当然なことです。しかし、そういう数え方を超えて考えてみたいのです。変化の多いこの季節に主の復活が祝われるとはどういうことなのだろう?主の復活は、春に起きるこれらの変化を遥かに超えた大いなる変化をもたらす出来事であるということではないでしょうか。生の終わりは死であり、死を越える術はほかにないと思って生きる人に、そうではない、死を越えて永遠に生きる道があることを伝える出来事、それがイエス・キリストの死者からの復活なのです。
さて、復活後、マグダラのマリアに現れたイエスは、主に会って喜ぶ彼女にこう言われました。「私に触れてはいけない」と。この言葉は彼女にとってどんなに思いがけない、悲しい言葉だったでしょう。生前、近くで、尊敬の思いをもって親しく触れ合っていた彼女にとって、「私に触れてはいけない」と言われる、それほど辛い言葉はないと思うのです。しかも、死んだと思っていた主が、今、自分の前におられるのです。再び会えたその喜びを、力いっぱい抱きしめて現したいのに、主は「触れてはいけない」と冷たい一言。
もう何かが変わっていたのです。イエスは彼女に、今までとは異なる関わり方を求めておられます。マグダラのマリアは、ペトロやヨハネ、ヤコブのような弟子たちよりも、イエスの最も近くにいて、イエスの教えに聞き、イエスの働きを積極的に支えた人です。イエスが十字架の上で死を成し遂げられたときも、その場を離れず、母マリアと一緒に見守っていました。それだけ親しく家族のように深い関係で結ばれたイエスから大きく影響を受けた女性です。
それだけ影響を受けた存在だからこそ、その人との間で生じる変化を受け入れる、受け入れて生きるということです。長い間共に生きた、愛する人が事故や病気で死ねば、その死を悲しくとも受け入れていくのは最も近くにいる家族です。それは、体を持った存在との別れ、フィジカルな接触がもはや不可能になるという事実を受け入れるということです。
しかし、イエスは復活して、体を持った姿でマリアの前に現れました。それなのに「私に触れるな」と遠ざけられる、死の別れよりももっと悲しくなるこの辛い一言。なぜなら、私たちは、愛する者との間の距離の取り方が、あまりにも自己中心的だからです。愛しているからという理由で相手を思うように動かせようとします。それは、愛ではなく人間の愚かな執着に過ぎないのに、子どもに対しても、パートナーに対しても、神さまに対しても、自我をはってしまうのです。
マグダラのマリアもそうでした。死なれたイエスの遺体が無くなったのを知り、それを取り戻すために必死でした。見える者、感覚に触れられるものこそ確かなものと信じる限り、人は、死がもたらす肉体の別れから来る悲しみや恐れから解放されることはできません。
その私たちが、今、イエス・キリストの復活をお祝いしています。四旬節の間、皆様に何か変わったことはありましたでしょうか。祈りのテーマを設けて過ごされたと思うのですが、それこそ春の変化の多い時期に、十字架の道を歩かれるイエスさまとどんな交わりが出来ましたか。
マグダラのマリアは、目に見えるイエスの体に執着して探していたために、復活の主に出会うことができました。彼女はイエスを探し求めたのです。イエスへの必死な思いが、たとえそれが彼女の執着だったとしても、その願いが適えられたのです。そして復活の主から、「私に触れるな」と言われ戸惑いながらも、起きている変化を受け入れ、見えないもの豊かさへ導かれています。
私たちは、あまりにも変化を恐れます。自分の心の扉をイエス・キリストが入って来て交わる場としてオープンすることを躊躇してしまいます。慣れた生活パターン、慣れた人たち、慣れた場所、慣れた話し方、慣れた考え方…習慣になっていて身に慣れたことを好んでしまいます。イエスさまが私の前に現れて、新しいものがある、崇高なものがある、もっと豊かなことがあるとお話されても、きっと、私たちは断ることでしょう。今のままで足りている、今さら違うものを受け入れて変わった生き方をしたくないと。イエスさまがもたらすものを厄介なものと思ってしまうのではないでしょうか。
今のままでいいという在り方が、結局、依存的な生き方を産み出していきます。そうなると、霊的成長が止まってしまいます。
4月20日は地図の日で、その日の新聞に富士山の背丈が伸びたという記事がありました。日本の地図が造られたのは200年前。六人の人が往復3,200キロメートルを180日間歩いたそうです。歩いた歩幅をメートルに換算して距離を測ったようですが、その中に山は富 士山だけが入ったと。ところが、富士山の標高がそのときより、衛星で測れる今は56センチほど高くなったと。
富士山が成長しました。私たちも成長しなければなりません。教会は霊的成長が止まると、ただの人の集まりに過ぎなくなってしまいます。霊的成長を成し遂げるためには、変化を受け入れることです。新しい考え方、新しい出会い、新しい道を常に歩き始めること。イエス・キリストとの交わりはそれに尽きると言っていいのでしょう。そしてそれは、信仰生活だけでなく、家族や友達との関係も同じです。
イエスを必死に探し求めたマリアは、イエスさまから「私に触れてはいけない」と言われ、以前の関係が否定されたようでしたが、イエスとの間に程よい距離ができました。それは、無駄な距離ではありません。程よい距離感の中でこそ、人は、神を神として拝み、人を人として対等に見つめることができます。同時に、自分が自分としていられるとても大切な距離感なのです。
マリアは、今まで味わったことのない大きな変化を経験しています。蓋をしていた心の扉が開かれ、そこから命の水が湧き出るような、永遠を見つめながら生きる道が拓かれました。死への恐怖は追い出され、自由になりました。ですから、彼女は復活の主から託された言葉を隠れている男の弟子たちに伝えるために走りますが、もう恐れはありません。
実は、私たちは、いろんな変化の中を生きています。子どもが成長して離れて行く、歳を取って白髪が増える、体の機能が衰えていく、気候変動が激しい、愛する者との別れ…変化のただ中を生きているのです。変化に適応する力が私たちの中にはあるのです。ましてや、神さまとの関係の中でもたらされる変化を、恐れることはありません。今の自分も、やがては、見えない者となります。今の交わりから永遠の交わりの中に招き入れられていくときに、目に見える体はなくなってゆくのです。そういう事実を現実の中で受け入れて生きる。それは私の思いのよらない、むしろ反するような死と復活の理解です。それを喜んで受け入れていくのです。
主の復活は今や私たちの信仰、生の根拠、源泉であり、力です。死の力を弱くしたからです。ですから「私に触れてはいけない」というマリアへの復活の主の言葉は、同時に私たちへの招きであり、私たちの思いを超えた新たな生、喜びへの招きの言葉です。そして、すがりつくような生き方から、この自分の足で歩いていく新たな生、その歩みのために、復活の主との交わりこそ、新しい命の力になります。
さあ、復活して私の心をノックしておられる主に、心の扉を開きましょう。皆様のこれからの歩みが復活の主との交わりの中で、より豊かな歩みとなりますように、復活の主イエス・キリストの御名によって祈ります。
Youtubeもご視聴下さい。