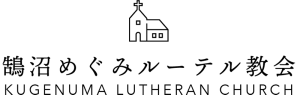ノー・アザー・ランド

2025年3月16日(日) 説教
四旬節第2主日
ルカによる福音書13章31~35節
ノー・アザー・ランド
先ほど拝読された福音書には、ガリラヤ地方の領主ヘロデと、そこから出て旅をするイエスとの間のやりとりがありました。これは、四つの福音書中でルカ福音書だけが伝えていることです。
何人かのファリサイ派の人が来てイエスに言います。「『ここを立ち去ってください。ヘロデがあなたを殺そうとしています。』」(31節)と。聖書にはイエスとファリサイ派の人たちとの関係があまり良く書かれていないので、ここでのファリサイ派の人たちはイエスにとても親切であるように見えますが、実はそうではありません。このファリサイ派の人たちも、イエスを殺そうとしているヘロデと同じように、イエスなどはこのガリラヤ領から早く出て行って欲しいわけです。その思惑をイエスさまは知っておられました。ですから、「『行って、あの狐に、『私は今日も明日も三日目も、悪霊を追い出し、癒やしを行うことをやめない』と伝えよ。』」と強く言われたのでした。
ここでイエスさまから「狐」と呼ばれているヘロデとは、当時、ガリラヤとヨルダン川を挟んだペレアの領主であったヘロデ・アンティパスのことです。彼はヘロデ大王の息子ですが、母親がサマリア出身だったので、王位継承にも母親の出身地が影響し、外れてしまいます。また、異母兄弟のヘロデ・フィリッポの妻へロディアを妻としたために、洗礼者ヨハネから律法に適っていないと叱責され、結局、ヨハネを殺してしまいます。王座はもちろん、のちに領主の座からも降ろされたアンティパスは、妻へロディアとともに流刑地に流され、そこで死にます。生まれ育った複雑な背景や、欲望を膨らましたことが、悲しい結末を迎えたのでした。
今日イエスさまが「狐」と呼んでいたこの頃は、まだヘロデがガリラヤの領主だったので、その力が及んでいたときですが、しかしイエスさまは、頑固として、ヘロデやファリサイ派、つまり、政治と権力が何と言いようと、自分に委ねられた働きを辞めない。「悪霊を追い出し、癒やしを行うことをやめない」と強くおっしゃって、それを「あの狐に伝えなさい」と言われたのです。
このイエスさまのお姿に、教会(=信徒)は従う群れとして集められています。しかし、今日のこのイエスさまのお姿は、今の教会に対して、「何を恐れているのか」という問いかけになっていないでしょうか。イエスさまは神さまを恐れ、神さまに全信頼をおいて、神の国を推進するために、つまり、十字架と復活の道を進めるためにエルサレムへの上りの道におられるわけです。十字架と復活の道とは、自分の命をささげるための道です。私たちはこのイエスさまに倣っているのか。そうでないなら、いったい、私は、何を大切にし、どこへ向かって歩いているのか、問いかけが必要と思います。というのは、私たちは、糧にならないもののために命をかけている場合が多いからです。
それからイエスさまはエルサレムのために嘆かれます。
「エルサレム、エルサレム、預言者たちを殺し、自分に遣わされた人々を石で打ち殺す者よ」(34節)と。
「エルサレム」は「エル」と「サレム」という言葉が組み合わされています。「エル」は神を表し、「サレム」は平和を表します。二つを合わせると、「神の平和」と言う意味になります。エルサレムは神の平和を象徴的に現わすところです。世界が神の平和がわからなくなったら、エルサレムを見つめればいいと言うくらい、大切な場所です。
しかし、今、どうでしょうか。私たちは神の平和を求めてエルサレムを見つめたくなりますか。今、直接、エルサレムが戦地にはなっていませんが、エルサレムで、ハマスを討伐するつもりの、いろんな作戦が話し合われているのです。その結果、ガザ地区の住民を巻き込んだ戦いが長い間続きました。自分たちの理念を達成するために、あまりにも残虐な行為を行い、罪のない人々を巻き込みました。決してゆるされない行為が行われました。
しかし、今日、ルカ福音書が伝えているのは、このような行為は昔から行われていたということがわかります。イエスさまは怒りを込められた言葉で嘆いておられます。「エルサレム、エルサレム、預言者たちを殺し、自分に遣わされた人々を石で打ち殺す者よ、めんどりが雛を羽の下に集めるように、私はお前の子らを何度集めようとしたことか。だが、お前たちは応じようとしなかった」(34節)。
先日、パレスチナ人の苦悩を描いた「ノー・アザー・ランド」(故郷はほかにない)という映画を観ました。この映画は、第97回米アカデミー賞の長編ドキュメンタリー部門を受賞しました。イスラエルの占領下にあるパレスチナ自治区ヨルダン川西岸に住むパレスチナ人の苦悩を描いた作品です。イスラエル軍がブルドーザーで家や学校を破壊し、住民たちが家を追われる映像が治められています。子どもの頃からこうした迫害を経験して来たパレスチナ人活動家バーセル・アドラー氏は、2023年10月まで、4年間、毎日、カメラに映像を収め、世界に発信しました。それをまとめたものがドキュメンタリー映画になり、受賞されたのです。
この映画には、アドラー氏の友人として、イスラエル人のユヴァル・アブラハームという青年が登場します。アドラー氏はアラブ系のパレスチナ人で、ユヴァル・アブラハーム氏はイスラエル人です。昔から敵対し合う民族同士ですが、この二人がとても尊い友情を見せていました。言葉にはありませんでしたが、その二人の姿を通して、「どうしたら人は分かり合えるのか?」ということが見ている人に投げかけられたと思いました。
アドラー氏は言います。自分の子どもたちは、暴力を恐れている今の自分たちのような思いをしないで生きる世界を求めて祈っていると。彼が祈り求めているように、私たちも、一刻も早く、パレスチナの地に神の平和が訪れることを切に願っています。そしてそれは、エルサレムが、神の平和という名の通りの役割を果たすときにこそ実現できることではないでしょうか。
いきなりブルドーザーが来て家が壊される。それに抵抗すると銃で打たれる。子どもたちが勉強している真最中に学校がブルドーザーで壊される。余儀なく家や学校から出されて、生まれ育った故郷を去る人もいました。
私たちは、意図的な武力によって住処を奪われたりすることはありませんが、自然災害や事故、または人間関係において思わぬことに見舞われるときがあります。家族を失ったり、お金を取られたり、家や持ち物を失い、仕事や健康を失う場合もありましょう。そういうとき、起きていることとどう向き合うのか。それを決めるのは自分自身なわけです。聖書の知恵を持って対処しなければ、私たちは、起きてくることの奴隷のように振り回されてしまいます。ヘロデのように、複雑な背景をもっていて権力と富を握りしめようとしなくても、物事が上手くいかないときに、自分自身を信じられず、意気消沈(いきしょうちん)してしまうのです。ですから、聖書は、常に私たちに述べます。『恐れることはない』と。つまり、あなたの心の平和を失うな!ということ。これが聖書の知恵なわけです。
ですから、今日イエスさまが嘆いておられるエルサレムとは、私たち、私たちの内面、心を見つめて嘆いてくださっていると言うことです。私たちの内面は神の平和が宿るところです。そこで人生が設計され、日々の計画が立てられて決断されます。いろんなことのピンチのときに、私がどんな決断をしていくのか、それによって私の周りが争うか平和になるかが決まります。ヘロデのように、グルと思ったものはすべて取り消そうとして、感情的な決断をしていこうとすれば、私たちは、いつ経っても自分の感情の奴隷としてしか生きられないのです。
その私のことをイエスさまは良く知っておられて、嘆いてくださっている。「エルサレム、エルサレム」と。ですから、このイエスさまの絶叫(ぜっきょう)は、私のためにほかなりません。イエスさまは、私の内面をことごとく知っていてくださって、涙を流しながら、祈ってくださっています。まるで故郷のない人のようにさ迷わずに帰ってきなさい、神の平和の中へお帰りなさい。そして、神の言葉によって力をつけて、周りの人々を勇気づける働き人になりなさいと。
私たちの故郷は地名で表すところだけではなく、私たちの心に宿られる神の国、イエスさまが歩いておられる十字架の道、そこにまことの故郷があります。その故郷を失ってしまえば、私たちの霊的歩みはさ迷い始め、先を歩かれるイエスさまを見失ってしまいます。ですから、心の中に宿る真の故郷へ帰って行くために自分の内面を見つめ、観察することを日常的なこととして行いましょう。そして、今日「エルサレム、エルサレム」とのイエスさまの嘆きに招かれている、そのことに心の耳を傾けることが出来ますように祈ります。
Youtubeもご視聴下さい。